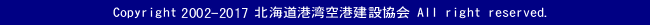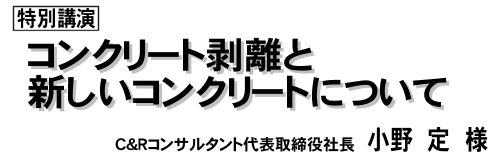|
ただいま紹介いただきました小野でございます。よろしくお願いいたします。
昭和47年、正確には1971年から、実はコンクリートの世界に関係しております。爾来、現在まで約35年近くコンクリート関係の仕事に携わっています。
私のメーンは、研究的なものもありますけれども、やはり現場を、私の現在のモットーもそうなのですけれども、現場を見るという、現場で確認するという、何があっても現場を見るというのを第一に置いております。そういったことで、現場を主体に実際のコンクリートの問題に対応していくということでやっております。
今回いただきましたテーマが、「コンークリートはく離と新しいコンクリート」ということですけれども、はく離の方はいいのですけれども、新しいコンクリートとはく離と関連づけてどう説明しようかということであくまでも北海道特有の凍害、初期凍害に伴うはく離ということに限定して、きょうの話をさせていただきます。
1.港湾施設とはく離現象
〇 港湾・海岸構造物における発生事例
〇 初期凍害によるはく離(スケーリ ング)
防波堤などの港湾、海岸構造物における初期凍害によるはく離は、通称スケーリングという言葉で言われております。一部、その前の状態をピーリングだとか、そういった言葉で言われておりますが基本的には、専門用語的にはスケーリングというのが、はく離現象として言われている言葉です。
今回、はく離対策と同時に、沈下ひび割れをある程度皆さんが意識して考えていただきたいというのが私からのお願いです。
2.コンクリートで発生する変状
〇 変状とは
●施工段階の変状:設計・施工不良、ひび割れ
●供用段階:劣化、設計・施工不 良、ひび割れ
●予測できない段階:損傷
●ひび割れ
3.はく離のメカニズム
〇 はく雛の発生メカニズム(1)
●躯体表層部に水は浸透
●大きい空隙中の水が凍結
●小さい空隙中の水が凍結
●小さい空隙中の水が凍結する過程では
●大きい空隙中の氷晶により膨張 (9%体積膨張)が拘束される
●この膨張により
○ はく雛の発生メカニズム(2)
●静水圧が空隙の壁に作用
●引張応力が発生
●引張強度を超える
●ひび割れ発生
●繰り返し
●はく離、浮き⇒はく落に至る
○ なぜ港湾施設・海岸構造物ではく離が多いのか(1)
●高炉セメントB種が使用されている
●耐海水性、化学的抵抗性に優れているため
●初期に十分な湿潤養生期問が必要
○ なぜ港湾施設・海岸構造物ではく離が多いのか(2)
●湿潤養生期間が3~5日
●耐久性指数が、養生7日の半分程度
●表層部が凍害を受けやすくなる
●型枠の存置期間、脱型後の養生によりこの影響が出てくる
4.はく離対策
○ よいコンクリートとは
①均質性
②強度
③ワーカビリティー
④耐久性
○ 高炉セメントB種を使用する場合の対策
●湿潤養生を十分にとる
●型枠存置期間7日以上
●存置期間が短い場合には、脱型後、湿潤養生を速やかに継続する
●あるいは、表面に改質剤などを散布し、躯体の表層を綴密にし、水の浸透
を抑える
●沈下ひび割れをなくす
5.新しいコンクリート
○ 基本的な考え
①材料的
②工法的
③材料と工法の組み合わせ
○ 新しいコンクリート(1)
●材料的
①高強度コンクリート
⇒水セメント比を小さくする
⇒高性能AE減水剤の使用
②高流動コンクリート
⇒結合材を多くして、強度を 高め、ブリーディングを少なくする
③繊維補強コンクリート
○ 新しいコンクリート(2)
●工法的
①高流動コンクリート
⇒結合材を多くして、強度を高め、ブリーディングを少なくする
②埋設型枠
6.まとめ
○ 初期凍害によるはく離は湿潤養生の影響大
●高炉セメントB種を使用する場合には
●湿潤養生期間を7日以上
●沈下ひび割れを防ぐ
●発生した場合には処置しておく
●十分な養生期問が確保できない場合の対策高流動コンクリート、高強度
コンクリート、繊維補強コンク リート、埋設型枠など
今日は、養生の話を結論的にしたかと思いますけれども、初期凍害によるはく離は、湿潤養生の影響が一番大きいのだということと、高炉セメントを使う場合、湿潤養生期間を
7日以上は何とか確保してほしい。本来、コンクリートはこうあるべきだという基本に立ち返って考えていただければ、かなりの部分は防げるのかと思います。100%防げるとは私は言いませんけれども、あとは皆さんの施工能力と技術力の差にかかっています。
|